2013年 08月 19日
脂質異常
脂質異常症とは?
気になる更年期と脂質異常症
更年期障害のひとつとして、加齢による血管の老化が挙げられます。 女性の「更年期」とは閉経前後の約10年間、平均して45~55歳を指します。更年期障害には、のぼせ、ほてり、しびれ、動悸、発汗、冷え、腰・関節痛、肩こり、頭痛、不眠、不安、憂うつ、苛立ち、食欲不振、肌の乾燥、かゆみなど、実に多くの症状があります。更年期障害とは?
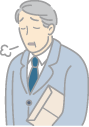 身体は「幼少児期」「思春期」「性成熟期」「更年期」「老年期」の5つに分けることができます。
身体は「幼少児期」「思春期」「性成熟期」「更年期」「老年期」の5つに分けることができます。
この「更年期」は、女性55歳頃、男性45歳頃を指し、この時期に身体に起こるさまざまな健康上の障害を「更年期障害」と呼んでいます。
以前は「女性の更年期障害」のみが取り立たされていましたが、近年男性でも、精巣間質細胞で生成される男性ホルモン「テストステロン」の減少により、女性の更年期障害と同じような症状が現れることが分かってきました。更年期とコレステロール値
血管が老化すると、血圧が高くなる、血管壁にコレステロールや中性脂肪などが沈着するなどの症状が現れてきます。男女共に、動脈硬化、脂質異常症、高血圧症などの疾患を引き起こす危険性が自然に高くなるということです。
女性の総コレステロール値は50歳以降に男性のそれよりも高くなる傾向があります。生理のある間は、女性が心血管病になるリスクはきわめて低く抑えられていますが、閉経後は急激にリスクが高まりますので十分に注意しましょう。女性の更年期と脂質異常症
これらの主な原因は、卵巣機能の低下に伴う女性ホルモン「エストロゲン」の減少によるホルモンバランスの崩れだと考えられています。
「エストロゲン」は「卵胞ホルモン」とも呼ばれ、子宮の発達、子宮内膜の増殖、乳腺の発育などを促進するほか、骨や皮膚の代謝やコレステロールにも深く関係しています。
「エストロゲン」には血液中のLDLコレステロール量を抑え、HDLコレステロールの合成を促進する効果があり、血中のコレステロールを調整してくれます。
このため、「エストロゲン」が減少する更年期の頃から血中のコレステロールが増加し、脂質異常症になる可能性が高くなるのです。